キース、ブラジルと共演
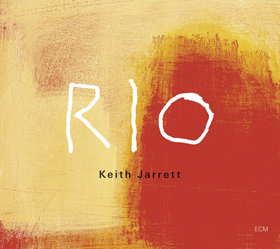
キース・ジャレットの最新作のソロ・ライヴは、ブラジルのリオデジャネイロでの録音だ。記憶の中にジャレットのラテン世界でのライヴ・アルバムはない。それどころか南米での公演は80年代に一度しかないという話を聞くと、これはもはや「事件」ではないだろうか。
確かにラテンの空気は、ジャレットの音楽とは馴染まないという印象がある。しかし、だからと言って南米でジャレットの人気がないと考えるのは早計だ。実際、この録音のジャレットの演奏に対する客席の細やかな反応、そして熱烈な拍手は、どこで生きようとも人の美意識は変わりはないと教えてくれる。むしろ、この演奏で微妙な変化を感じるのはジャレットの方だろう。演奏は2枚のCDに15曲収録されているが、どこかゆるやかで自然な音楽の時間が流れている。近年ジャレットの演奏は、恐ろしく緊迫感に満ちた濃密なリリシズムの世界から、別の世界に移行、あるいはそうせざるを得ない状況にあるように思うが、これはそんなジャレットの今が、とてもいい感じで伝わってくる。
何よりも曲の多さが、メロディーとの爽やかな距離感のようなものを生んでいる。ジャレットのソロというと曲のない即興演奏と受け止められているが、けれどあの名作『ケルン・コンサート』の長尺の演奏と最近の演奏を同じように受け止めることはできない。なるほどどちらも曲名がないのは同じだが、長編小説と短編集くらいの世界の温度差があり、さらに言えば明らかに既成の曲の演奏と言った方がいいものもある。むろん、どこまでが曲でどこまでが即興音楽という厳密な区切りのようなものはどこにも存在しない。演奏すれば音楽であり、本来それ以上でも以下でもない自由な世界なのだ。この15の断片は、そんな自由をシンプルに謳歌しているジャレットの世界と言っていい。ウイットの効いた突然の演奏(曲)の終止に沸く客席とのコラボが、どこかラテン的な世界にも繋がっている気がする。これは楽しいぞ。



