〈コミュニズムとしての映画〉は可能なのか? /5月革命とその前後を巡る映画人の手紙
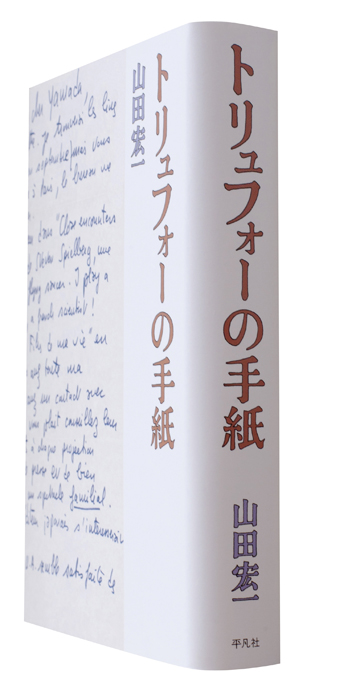
長らく絶縁状態にあったかつての盟友の死を受けてジャン=リュック・ゴダールは、ディドロやボードレールから連なるフランスにおける偉大な美術批評の系譜に「フランソワ」を位置づけ、僕らの感動を誘ったものだが、書き手としてのフランソワ・トリュフォーにはもう一つ「最後のエピストリエ(書簡文学者、筆まめな人)」という顔があった。ソーシャルメディアが活況を帯びる現在、今や書簡文学など消滅しつつあるのだろうが、強い絆で結ばれた異郷の友人(本書の著者)に宛てたトリュフォーの手紙が表紙に印刷されており、たとえその内容はわからずとも、僕らはそこに書き手の肉体の痕跡を読み取ることができる。『恋のエチュード』や『アデルの恋の物語』といったトリュフォー作品にあって手紙は、登場人物が憑かれるように白紙に刻む身体性の痕跡としてあり、インクは肉体から滴り落ちる血の代用品だった。そう、俳優及び映画作家の身体性の刻印=痕跡であり続けたトリュフォーの映画は、僕らに宛てた手紙だったのかもしれない……。 『トリュフォーの手紙』は、二つのエンディングが立て続けに現れる映画のようだ。最後のエンドマークは映画作家の生涯の早すぎた終りを著者との手紙のやり取りを通し描くものだが、少し遡って読まれる最初のそれはトリュフォーとゴダールの友情の崩壊と重ね合わされる。1973年に交わされた両者の手紙全編を読むことができ、相手の皮肉な口調の批判に応じたトリュフォーの返信がとりわけ凄まじい。かつて「フランス映画の墓掘り人」と恐れられた批評家時代の喧嘩作法が不意に蘇るかのようだ。その後、尊敬する二人の師の大喧嘩によって身を引き裂かれる状況に陥った俳優ジャン=ピエール・レオーの苦悩を巡る記述が続き、トリュフォー亡き後にゴダールが綴った――しかしなぜか投函されなかったらしい――レオー宛ての手紙が最初のエンドマークとして置かれる。「フランソワの人生(la vie)も、そしてわたしの人生も、きみのおかげなのだし、きみあればこそだったんだよ」。以前に読んだことのある文面のはずなのに、涙をこらえきれなかった。もちろんヌーヴェル・ヴァーグの両雄が育くんだ厚い友情とその瓦解を本書で追体験してきたからで、遅まきながら亀裂の修復に努めるゴダールの思いが滲み出るからだろう。異なる文脈で改めて読み直されるとき、既知のはずの文章が未知の輝きとともに蘇る。僕の涙はゴダールの文章によるものである以上に、山田宏一の手腕によるものなのだ。
1968年の5月革命の余韻の下で、二人の映画作家は袂を分かつのだった。単純化すれば、ほぼ全ての商業映画を敵視する革命家ゴダールの目に、トリュフォー作品が救い難い反動と映るに至ったのだ。歴史的な分水嶺である68年5月を13歳で迎えた映画作家オリヴィエ・アサイヤスによる書物は、革命を予言する書ともされた『スペクタクルの社会』の思想家ギー・ドゥボールの妻に宛てた手紙との体裁をとりつつ、実際には、68年を知らない若い世代に向けて書かれている。この本で読まれるのは、「革命」から遅れた者に固有の孤独やニヒリズムもあらわな「5月の後の青春」であり、ヌーヴェル・ヴァーグの両雄を仲違いさせた刃が今度は後続の世代を内側から二つに引き裂く。革命へと駆り立てられる実践に伴う熱狂と、その熱狂を冷やかに見つめる理論的で日常的な内省。「乗り越えがたい解答が示された後でも人間は生き残る」のであれば、革命が破綻し、「ドイツやイタリアや日本の同志」がテロリズムへと突き進む「鉛の時代」──映画作家が『カルロス』で取り上げた時代――にあって、しかしそれでも革命を志向する「絶対自由主義」はいかにして生き残りを図るのか。
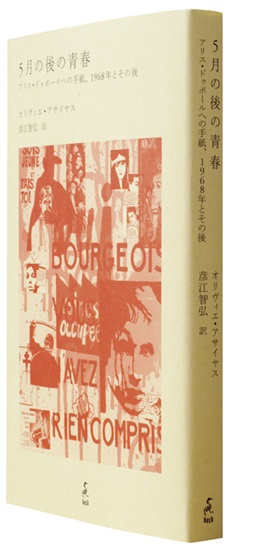
アンディ・ウォーホルとヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ジョージ・オーウェル、ギー・ドゥボール、セックス・ピストルズ(ヌーヴェル・ヴァーグの映画ではなく、ニュー・ウェーヴの音楽!)……。映画についての記述は末尾近くまでほとんど現れず、だからこそ著者が自らに巣食う亀裂の修復を映画に託す経緯が感動的なものに思える。つまり本書でも書き手の手腕に基づく見事なエンディングが準備されるわけだが、アサイヤスの仕事は『シックスセンス』の類いではないのだから、ここでその結末に触れてもネタバレなどと責められることもないだろう。彼にとって映画は「疎外されていない集団作業が存在しうる」ことを示し、「世界との、また社会的な集団実践との和解を可能にしてくれる一つの道」をようやく開いてくれるものだった。「プルーストの後にも、ジョイスの後にも、小説は存在し、マラルメの後にも詩は存在する」。同様にヌーヴェル・ヴァーグの後にも映画は存在するが、彼らの戦いの後に広がる「荒涼たる光景においては、すべてが再構築されなければならない」。革命の(不)可能性という「乗り越えがたい解答」あるいは「荒涼たる光景」から、かつてトリュフォーとゴダールを決裂させた「コミュニズムとしての映画」という主題が不意に再構築され、二人の和解をより強固なものとするかのようだ。



