サカナクション(4)
「〈みんな、目を瞑れよ〉という言葉で4つ打ちが始まる――そんなバランス感覚が、サカナクションの着地点」
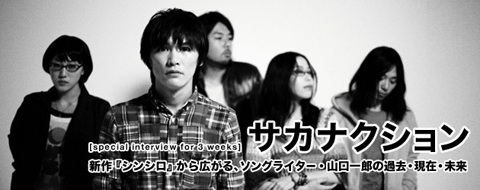
――続いて歌詞の話に移りますね。詞と曲では、どちらが先にあることが多いですか?
山口 詞が先っていうことはほとんどないですね。僕、歌詞と詩は書き方が別なんですよ。歌詞は俳句と一緒で、言葉数も決まってるし、その短い言葉数のなかで、どれだけきれいなメロディーを作れるか、何ていう言葉をキーワードにするか、っていう作り方をするんですけど、詩を書く時は、言葉数も気にしないでいいし、自由に書けるじゃないですか。そういう詩はいっぱい書き溜めてあって。一行二行しか書いてないけど、そこが僕の別の脳みそみたいな感じで、そこからインスピレーションが湧いて、詞を書いたりする。
――では、詩や歌詞を書く上で、山口さんに影響を与えているものは何かありますか?
山口 僕、いま28(歳)なんですけど、22から25ぐらいのときが、一番多感な時期だったんですよ。その頃に感じてたものが、いまのすべて。僕、18から25ぐらいまでのあいだ、文学に対して一切、手を抜かなかったんです。真摯に向き合ったし、自分自身にも甘えを持たなかった。自分だけじゃなく他人にも厳しかったんですけど、そのときの経験がいまに生きてる。だから、歌詞を書くときに何かから影響を受けているとしたら、過去の自分が書いた言葉だったり、その頃に考えていたことですね。モラトリアムから抜け出しかけてる自分が当時に戻って、同じことについて語るならどう言うだろうな?って。
――ああ。
山口 その頃は極論だったけど、いまはもっと緩和して言える。そして緩和して言うことが、マスに対して発する言葉の親切感になったりする。昔の僕の極論に賛同してくれる人は一部だろうけど、そこで言ってることの本質は正しいから、いまの僕がそれを歌にすれば、きっと本質だけをきちんと人に伝えることができるんじゃないか、って考えるようになって。
――文学に対してまったく手を抜かなかったっていうのは?
山口 本を読むのはもちろんですけど、文学の力を信用してたっていう感じがありましたね。
――言葉が持つ力を信用していたということ?
山口 文学や言葉が、政治や国さえ変えると思ってた。そう思えるぐらい、僕は文学を信用してた。誰かが20年、30年かけて研究したり考えたりしたことを一冊の本で知ることが、当時の僕にとっては大切だったんですよ。だから、その頃の自分が書いたことっていうのは、僕が読み続けてきた作家の考えにピンポイントで影響を受けている言葉――僕からOKサインが出た言葉、共感した言葉だから、すごくデカイんですよね。いまは「こういう意見もあるよね」って文学に対して斜に構えてるところがあるけど、当時は「自分はここだ!」みたいに、何にでも食いついていく積極性があった。ひとつの気持ちを知るために昔の文献を読んだりとかして、ホントに信頼してた。文学に勝るものなし、って思ってた。
――ピュアですね。
山口 そうかもしれないですね。そういう姿勢のまま音楽に接してたから、当時は歌モノを聴けなくて。テクノとか、音のループにおける絶対性みたいなものを信用しつつ、一方文学では、まったく別のところで活動していて。それがぐるぐる回っていって、サカナクションになって、どんどん混じっていった感じがありますね。

――現在の山口さんの作風やサカナクションのサウンドから考えると、その話は何だか説得力がありますね。
山口 昔は、言葉のわかりやすさとかどうでもよかったんですよね。親切な歌詞なんて書かなくていいって思ってたし、わかんない人はわかんなくていいよ、って思ってて。ファースト・アルバムに“フクロウ”っていう曲があるんですけど、詞に関しては超不親切なんですよ。自分が言いたいことを直球で言ってないから、どうにでも捉えられる。でもいまは、こういう言い方にするとわかりやすくなるだろうな、って考えたりするし、僕のなかの成長だと思うけど、だいぶ変わってきてますね。
――今回のアルバムでは、トータルで言えば、人の本質について書いてますよね。自分をとおして、人そのものを描いてるというか。
山口 僕は、基本的に人ありきだと思ってるし、そこが僕の原点。人に対する自分の感覚って、その時期その時期で違っていて、大雑把なことを言うと、他人とまったく接したくないときもある。そういう時期も自分だし、たくさん人と知り合いたいと思ってる時期も自分。時期によってニュアンスは違うけど、〈人〉についての普遍的な部分を切り抜いたものが、僕の詞の細部にはいつも入っている気がしますね。東京に来て、やっぱり自分たちだけじゃ、音楽は伝えられないってこともわかったし。
――と言うのは?
山口 たとえばライヴは、自分たちが演奏してるところだけを見せても、伝わることって4割か5割だと思うんですよ。そこに照明があって、PAがいて、いろんな助けがあってひとつの絵を表現するものがライヴだと思うから、最近は「人と関わることがすごく大切だ」って思ってて。昔は「何なら照明もPAも自分で覚えるよ」「全部ひとりでやるよ」っていう気持ちだったけど、いまは、照明とかPAとか、それだけに命をかけてる人と一緒にやることで、自分にはないものを表現してもらえる、って思うようになった。そういう部分が昔よりも強くなったから、人に対する見方もなんか融和してるっていうか、人色(ひとしょく)っていうんですか(笑)? が、強いのかもしれないです。
――『シンシロ』は、歌モノとしてもダンス・ミュージックとしても攻めた仕上がりになっていて、サウンド面ではかなりオープンになってますけど、歌っていることは必ずしも開いていないですよね?
山口 うん。
――どんなにカラフルでエレクトリックなサウンドでも、サカナクションの音楽には独特の人間味があって、それは歌詞だけ、音だけから生じるものではない。言葉とサウンドが混じり合うことによって、初めて生まれる〈人肌感〉だと思うんですよ。そこが私から見ると、エンターテイメントとアンダーグラウンドの中間点なのかな、っていう気がするんですよね。
山口 そうですね。確かに、そこが着地点だと思いますよ。これからも、僕が詞を難しくすればするほどアレンジはわかりやすく、詞をわかりやすくすればするほどアレンジは難しくなる気がするし、そのバランス感覚が、エンターテイメント~アンダーグラウンド間の重心の移動だと思うんですよね。「さあ、みんな踊ろうよ!」みたいな言葉で4つ打ちが始まるんじゃなくて、「みんな、目を瞑れよ」って言って4つ打ちが始まるような、そんなバランス感覚。そういう音楽のなかには言葉の持つ力が存在していると思うし、だから、サカナクションはやっぱり歌モノなんですよね。……すごくいいことを教えてくださいましたね(ニッコリ)。いま、少しだけこのアルバムを俯瞰で見れた気がします。
※来週は、山口一郎による全曲解説をお届けします!!
- 前の記事: サカナクション(3)


