柿沼康二

《喰》(2011)
「きみはミュージシャンだよ」といわれるんです。
金沢21世紀美術館の一画に設けられた取材場所で、私は目の前に座った、書家でありアーティストである柿沼康二に開口一番「この取材では音楽の話をしましょう」と話しかけた。さきほどまで、サッカーの元日本代表である中田英寿氏とキュレイターをつとめる秋元雅史館長とのアーティスト・トークを終えたばかりの柿沼康二は、私がそういい終わらないうちに、「音楽の話! それは疲れないッスね」といって笑った。
理由はないわけではない。私は書については、高校の選択授業で書道をとって以来、筆ももったことのない門外漢にひとしい悪筆の者であるが、メディア向けに開催した初日前日のガイダンスで、金沢21世紀美術館の1~6室までの大小の方形の空間と、ゆるやかにカーヴした壁面の第14室を使った『書の道「ぱーっ」』展を柿沼康二とともにめぐりながら解説を聞き、いや、聞くまでもなく、書という表現形式の美しさと自(在)由さ、筆使いに潜む音楽によく似た一回性、瞬間を圧縮する力と空間への働きかけを感じ、そのことばが口をついた。
「“文房四宝”、つまり筆、硯、紙、墨のなかでも僕の場合、紙は省けなくはないから、音楽は三つめくらいにもってきてもいいくらい重要で、それで自分を覚醒させているところはあるんです。僕は音楽家の友人が多くて、彼らにいわせると『きみはミュージシャンだよ』と。国内外を問わず。たとえば僕はアンダーワールドのカール・ハイドと知り合いなんですが」
――どうして知り合ったんですか?
「カールはフランツ・クラインを尊敬していて、彼自身もファイン・アーティストでもあるんです。クラインやその同時代のジャクソン・ポロック、マーク・ロスコなどは、井上有一という昭和の書家に影響を受けている。カールはたぶんそのことは知らないと思うんですが、自分の求めている世界に近いということでアプローチしてきたんですね。僕はもともとアンダーワールドが好きでしたし、彼が音楽監督をつとめたロンドン五輪の開会式を観て聴いて、あの祭典でセックス・ピストルズを流すイギリスの文化の豊かさも感じていたところに連絡が来た。それから頻繁にメールでやりとりするようになって、このあいだもカールに、広島県の熊野で筆をみつくろってプレゼントしたばかりなんですよ」
その交流はたんに親交にとどまらず、アンダーワールドの《Two Month Off》の歌詞の一節を引用した作品《You bring light in…》となり、岡本太郎の作品というよりも存在そのものに着想を得た、本展の表題でもある《ぱーっ》をはじめ、《一》《心》といった基調にもなった作品を掲げた第1室に続く2室に展示されている。楷書、行書、草書、仮名の書き分けによる古典的な《万葉の四季》、NHKの大河ドラマの題字《風林火山》、文字そのものが琳派を象る《風神雷神》、漢字や仮名、片仮名、3500年におよぶ書の歴史のなかでくりかえしとりあげられてきた私たちが日ごろ使う文字にかこまれ、アルファベットによる「書」の横書きの直線的な文字列はそのダイナミズムゆえ、タポグラフィにみられる意匠(デザイン)的な側面よりむしろ、形態と意味が一体になった文字への確信をうかがわせる一方で身体性からくる一画ごとのゆらぎはそこから逃れる導線を示すようでもある。
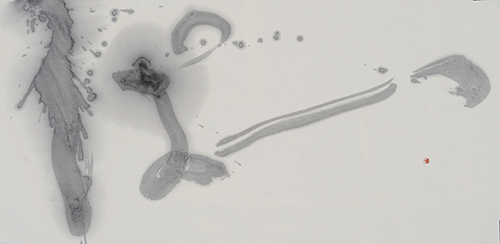
《ぱーっ》(2011)
《You bring light in…》は柿沼康二の業のひとつであるトランスワークによるもので、これは同じフレーズをさいげんなく書き連ねることで差異を反復する手法なのだが、出品作品のなかでも最後から2番目にできたこの作品でトランスワークは新しい局面に入ったと柿沼康二はいう。
「これは“いきていきていきて――”“おまえはだれだおまえはだれだ――”と書いていく一連の作品のひとつなんですが、これまでだと文字をツブすスタイルだったんです。空間を埋めつくすというか。それがはじめて、字間と行間をとった作品になったのが自分でも意外で、自分のなかでかなり定着していた表現をいい意味で浮遊させるきっかけになる作品かもしれないですね。次は《You bring light in…》を大きな表現にしたい。書いていない字間、行間に深い意味合いを込めたいと思っています」


